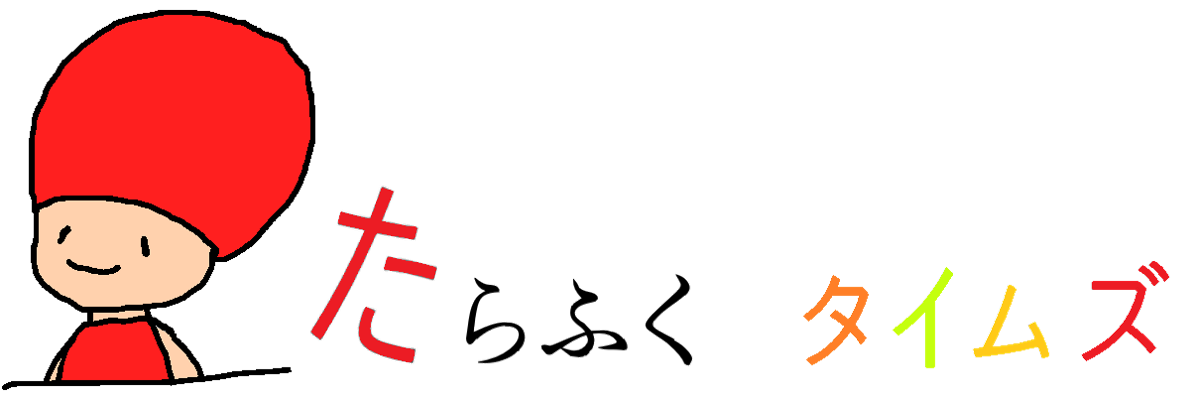2.親の遺志をつがなければならない子とたそがれの午後5時
わたしはケイ。同期のみんなはおケイという。地獄耳のおケイなんていうやつもいる。かげでいっていたってムダ。どんなかげぐちだって、わたしはききつける。
ここ、基地の大食堂のはじっこで、スプーンを落としてもききつける自信、ある。
それにしても、きょうの戦闘、なんか変。
わたしは食堂のテーブルに片ひじついてもの思いにふける。
セルボさんは、途中でかたまっちゃったし、ミラ指揮官殿も、セルボさんのサポート指示がおくれたんじゃないかな、って思う。
ああ、そのセルボさんが食堂にはいってきた。
コックさんとすれちがいざま、あいさつを交わしているし、けっこう社交性、あるんだなあ。
そんなことを考えながら、ぱくっと何かを口にすると、じわあとひろがる嫌な味!
「なにこれっ!」ぺっぺっ、お皿にはきだすとトマトのかけら。うわあ、トマトなんて食べたの何年ぶり?
「おケイ、嫌いなトマトなんか食っちゃって。どしたの? ぼうっとしてんじゃねーの?」アルトがわたしを指さして笑う。
「地獄におちろ!」
「おお、こわ!」
「今日、だれかセルボさんの近くにいた人いない?」そうきいてみた。
「班長のそば……のし?」とラパン。もぐもぐと何やら食べながらいった。
「うん」
「後半、班長をサポートにいったけど、それまでは、ずっと右後方でぐちゃぐちゃやってたんだのし、ねぇ、アルト」
「ああ、そうだな、おケイはスナイパー同志だから近くにいたんじゃないの?」
「わたしは左翼側だったから」するとフロンテが、
「……ぼく、近かったかも……まん中らへんだったから……」とぼそぼそという。フロンテはいつだってぼそぼそはなす。
「どうだった? セルボ機のうごき」
「えーとねぇ、最初はふつうにうまくて……。いつものように。そして、つぎつぎ墜として、順調だった。でも……」
「なに?」
「なんか急に、動きがとまった。……機体の動きだけじゃなくて、狙撃がとまった感じで……」
「なにかきっかけ、思い当たるものある?」
「ちょっと、いま再生してみる……」そういうとフロンテは、宙を見上げて手にしたフォークで指揮するようにくるくる回し、しきりにまばたきをした。
これが彼、フロンテの特殊能力、名づけて超記憶力。
彼はありとあらゆる瞬間を記憶できる。そして自由に思い出すことができる。目にした映像、聞いた話や音楽、すべて彼の頭脳に収められている。
当然、セルボさんの調子が悪くなった時の映像も、思い出せる。
「ああ、これか……。赤い軍事ドローンを狙撃して、それが墜落していったあと……、セルボさんは攻撃をやめてる」
「赤いドローン?」私は驚いてきき返した。するとラパンが、
「へえ、赤って珍しいね、ケイちゃん。めだつもんね。わらしは好きだけど」ともぐもぐしながらいった。
「そうだね、あまりいないよね。赤いドローン……そいつがカギか……」
わたしの目のはし、ミラ様が食事を終え、トレーを持って、食器回収レーンに向かっていくのが見えた。
「あ、それじゃ、ごちそうさま」わたしは後をおいかけるため、あわてて食事をやめ、ガチャンと音をたてて立ち上がった。
「あれ? おケイ、もういいの?」とアルト。

「うん、ちょっと、トマトなんて食べちゃったから」とかなんとかいって、わたしはミラ様を追いかけた。