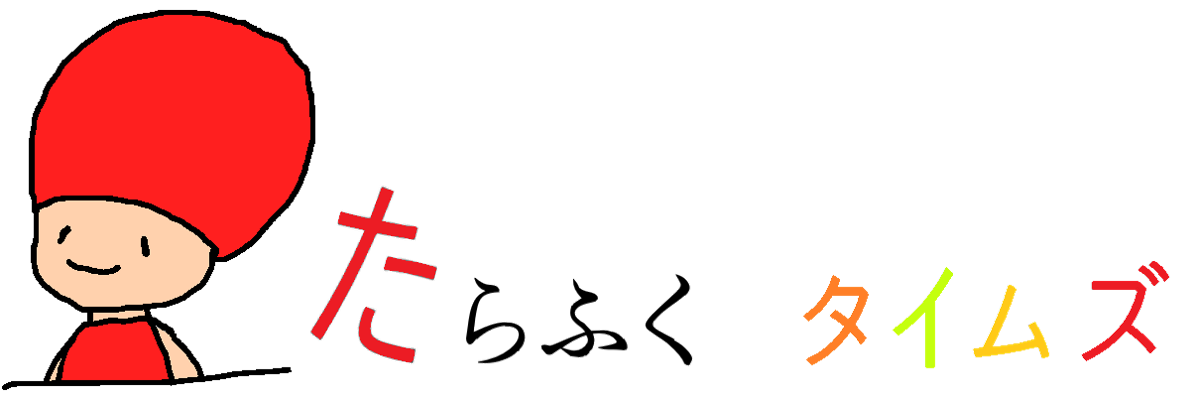3.セカンド・ハンターたちのつどいとマニアックな夜10時(つづき)
「さっき、落下するときの映像を鬼軍曹といっしょに確認して、墜落地点を特定したよ。明日、再捜索らしい」
「……鬼軍曹と……一緒だったんですか?」
「しかられたよ。何ぼうっとしてたんだ、って」
「僕……、見てましたけど、ちょっと動きが鈍くなったのは……、赤いドローンを墜としてからですよね」
「あ、ああ、そうだな。え、そこまで見てたのか」
「はい……。セルボさんの狙撃スタイルは好きなので……。おとりの射撃で誘導して、死角からしとめるところなんか……、ど、独特ですよね」
「相手に自分の機体をさらすのは苦手でさ、死角からしとめることばかりやってきたからかな」
「赤い機体なんて……、珍しいですよね。珍しくて動揺したんですか?」
セルボさんは首をふった。
「いいや、一年前までは多かったんだよ、赤いの」
「あ、……そうだったんですか」
「さすがに目立つし、標的になりかねないからかな、ある時から、ぱったり現れなくなったけどさ」
「だから……、僕みたいな新参者は、……見たことないんですね」
「いま残っている赤いのは、当時からの生き残りなんだ……。僕みたいにさ」
セルボ班長は、一年ほど前のジャコビニ半島攻略戦の生き残り。だから『生き残りの』セルボと呼ばれている。もちろん、めったなことじゃやられないという尊敬の意味で。
「じゃあ、なんか……親近感みたいなものでも……、感じたんですか?」
「まあ、そうだな。死角から赤いのを撃ち墜としたとき、まるで自分がやられたような気がして、恐ろしくなった。僕が『生き残り』って呼ばれているの、知ってるよな? ジャコビニ半島攻略戦の『生き残り』……」
「ええ、まあ……」
「ほんとうは『生き残り』なんかじゃないんだ。あのとき、当時操縦していた4機のうち、3機はやられたんだよ。一機だけが『生き残り』だったんだ。標的をもとめて前に前に進んで、気づいたら、スナイパーなのに相手に姿をさらしてた。その時はまだ、ミラ指揮官も着任前でさ、前の指揮官は僕が3機も墜とされたなんて気づいてなかった。そこから、そこから……」
セルボさんは口元を手でおおった。
「そこから、僕の機体が欠けた穴から、相手が侵入してきて、ジャコビニ半島の漁師町が、爆撃を受けたんだ。実際に犠牲者が出た戦いだった。こんなことはめったにない。だけど本当に犠牲者が出たんだ。リアルな犠牲者だよ。もし、それが僕やフロンテの家族だったらどうする?」
「……た、耐えられませんね」
「だよな。僕は耐えられない、本当の犠牲者出る戦いなんて、僕には耐えられないって、一年前のその時、僕は鬼軍曹にいった」
「なんていいました……? 鬼軍曹」
「僕がやめるともっと犠牲者が増えるぞ、って。だから逃げちゃいけないし、逃げられないんだ、肝にめいじろ、ともいわれた」
「……きつい……ですね」
「きついね。だけどその日から、僕の心の中には恐怖がすみついてしまった。やあやあ我こそは、みたいなスタイルはとてもじゃないけどできなくなった。死角からこっそり撃ち墜とすスタイルになったのも、それからだ」
「……そんなことがあったんですね」
「だけど、ときどき怖くて耐えられなくなる。そんなときは、かならずどういうわけか、鬼軍曹が表れて、僕にいうよ『恐怖を持ったら終わりだぞ』って。まちがいないよ、終わりだよ。もう、もう、終わりにしてほしい、そう思うよ」
急に修理ラボのドアが開き、鬼軍曹が表れた。
固まるのは僕の方だった。
「ここにいたのか、セルボ」
「は、はい」
「今日の戦い、恐怖に取りつかれたか」
「……はい」とセルボ班著は首をうなだれた。
「いつもいっているが、恐怖を持ったら終わりだぞ、そしてお前は戦いを続けるしかない。勝つまでは、な。お前がもし、この軍をやめるようなことがあったら、あの時、命を失った一四五人の国民たちがだまっちゃいないんだからな」
「は、はい……わかってます」セルボさんは震えていた。
「わかったら、もう、部屋にもどって寝ろ、ほら、フロンテもだ」
「セ、セルボさん、修理、……終わりました」と、機体をセルボさんにわたし、僕は修理ラボから出た。そして、自分の宿舎に戻りながら考えた。
ほんとうは赤い機体を墜としてから動きを止めたわけじゃない。戦いが終わって動きを止めたわけじゃないんだ。
地形を利用してセルボさんの操縦している六機は、うまく敵の死角に身を隠し、そこから相手に気づかれることなく迎撃した。そして、赤いのを墜とした後、そのうちの一機がするすると身をさらす位置に出てきたんだ。それからそのまま停止しホバリングしたのだ。
わざわざ一機が姿をさらす位置に出てきたのだ。さあ、撃ち墜としてください、とでもいうかのように……。